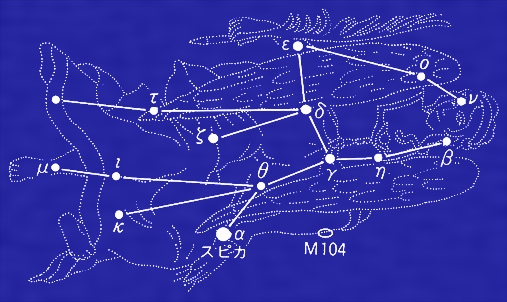ブッシュ(熱帯雨林)に飛ぶ前に、モンロビアにある会社オフィスにちょっと触れておこう。そこは暑さと喧噪でむせかえるようなモンロビアの市街地とは別世界。すべての部屋に冷房設備があり、ゆったりしたソファーのあるラウンジではいつでもテレビやビデオを見ることができる(これはアフリカでは普通ではない)。いつ停電するかわからない供給電力には頼らず、すべてを自家発電でまかなっている。
ビジネスの主要部分、つまり現地や海外の取引先とのコミュニケーションは基本的にオールソン一人でこなし、経理や細かい事務作業は、ドイツ人のハニングという男と、僕を空港まで迎えに来てくれたサングディにやらせている。
オフィスには「ゲストハウス」が併設されていて、モンロビア滞在中は僕にも個室が一つ与えられた。個室はもちろん冷房完備で、ホテルのようにシャワーやバスタブ、トイレなどが付属している。洗濯や食事など身の回りの雑用はすべて現地の使用人がやってくれる。
明日は任地であるサイノまで軽飛行機で飛ぶという前日、僕は会社のGMであるオールソンの家に招かれた。彼の住居は、モンロビア中心街にあるオフィスから、車で15分ほど走った郊外の海沿いにあるコテージだ。そこには彼の妻と三人の子供達が住んでおり、運転手や料理人を含めて数人の使用人を雇っている。なんとも豪勢である。
海岸には椰子の林があり、開け放たれた窓からは涼しい風が吹き込んでくる。この場所は、スプリングス・ペイン飛行場にも近く、時折、単発の軽飛行機が低空飛行しているのが見える。
「すばらしい環境ですね。ぼくもこんな別荘が持てたら最高だろうな」
僕がそういうと、オールソンは、
「気に入ったかい? この国で五年も仕事をしていれば、君だってこのくらいのコテージは建てられるさ。材料の木材は使い放題だからね」とこともなげに答える。

サイノにて: 洗濯物は地面の草の上に広げて乾かす。
彼のコテージから二十メートルほどしか離れていないところに、高床のこじんまりした別荘が見える。そばに大きなマンゴーの木があり、涼しげで居心地が良さそうな木造のテラスが、海岸の方に向かってつきだしている。テラスには、老夫婦が籐椅子に腰掛けていて、僕と目が合うと人の良さそうな笑顔で手を振った。
「あれはキャプテン・マラウィー。貨物船の元船長だが、今は引退して奥さんと一緒にここに住んでいる」とオールソンが説明してくれる。「ここが気に入ってしまって、母国のスペインに帰る気は全くないそうだよ。」
これは後日談。この数年後、内戦の激化で僕は一旦出国した。そして再度入国したとき、気になっていたマラウィー夫妻のことを知人に尋ねてみた。
マラウィー夫妻は、モンロビアが戦場と化してからも、このお気に入りのコテージを離れることを拒み続けた。ここを終の棲家と決めていたからである。そして最後には、家を明け渡すよう迫る反政府軍の兵隊の前に立ちはだかり、夫婦共々マシンガンで撃たれて亡くなったという。
僕がブッシュでのオペレーションについてオールソンと話をしていると、召使いのエッタと何か言葉を交わしながら一人の男が入ってきた。話し方から明らかにアメリカ人とわかる。
一通りの自己紹介が済むと、その男は直ちにビジネスの話題に入る。男の名はスティーブ・マッカーシー。どうやら彼も材木を港に運んでいるらしい。
話の内容から分かったことは、先日港を出港した船に積み損ねた丸太がかなりあって、それをオールソンの次の船に積み込んでほしいと頼んでいるようだ。
「うちが頼んである次の船までには、まだ一ヶ月近く間があります。虫に食われないうちに、何とか送ってしまいたいんですよ」
「オーケイ、スティーブ。明日はミスター・コシと一緒に私もサイノへ行くから、同じフライトで行こう。向こうへ着いたらすぐに港へ行って、丸太をチェックしてみる。」
「それはありがたい。今頃後悔しても遅いのですが、やっぱりあなたの言うように、レイニーシーズン(雨季)に無理して切り出すのはやめておいた方が良かった」
「まあ、何事も経験だよ。条件さえ整えば、レイニーシーズンだって切れないことはない。」
「あなたのアドバイスには感謝しています。じゃ、明日の朝スプリングペインで落ち合いましょう。」
マッカーシーはそう言うと、僕の方にも笑顔を向けて片手を上げながら、忙しそうに立ち去った。
こうした事情で、一人でサイノに飛ぶはずだった僕は、思いもかけずオールソン、そしてマッカーシーと一緒に行くことになる。ついでに港の貯木施設も見られるのは楽しみだ。
(つづく)