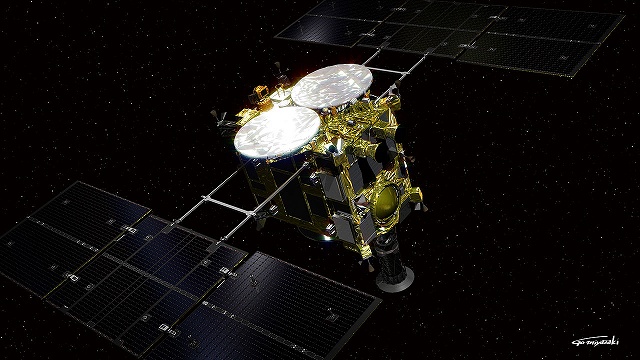もうあと少しで終わる平成には、人それぞれ複雑な思いがあるだろう。天皇陛下がおっしゃるように「戦争がなかった」のは事実だが、平成 7 年の阪神淡路大震災、平成 23 年の東日本大震災と立て続けの大災害に見舞われ、「平成」という名前が皮肉っぽく聞こえるようなこの 30 年間だった。そんな中でしきりに人々の口に上り、またテレビを中心としたマスコミにも取り上げられることの多いのが、人間同士の連携を表す「絆」とか「つながり」などの言葉だ。地震や水害などが起きると、この種の言葉が余計にクローズアップされる。
SNS などによる「ネット上でのつながり」もこれに含まれる。自分の家族や隣近所とのつながりが薄れて、いやあえて近所や親戚との「しがらみ」を避けることによって、人々はより自由になる。しかしその一方で孤独になってしまった人々が、遠く離れた見ず知らずの他人との「架空のつながり」に夢を求め、現実の人間関係はさらに希薄さの度合いを増す。そうした現代社会の「ひずみ」とも言える現象に危機感を覚える人は多いと思うが、「だからどうすればいいんだ?」と聞かれれば、明快な回答などない。
そんな閉塞感の中で、いま「縄文時代」が静かな注目を浴びている。縄文時代を扱った書物が数多く出版されており、縄文の文化について様々な興味深い視点が提供されている。縄文時代は、ぼくたち日本人の原点だ。いまいちど原点に返って、人間同士のつながり、そして人間と自然との関わりを見直すときなのかもしれない。景気回復や経済発展よりももっと大切なものがあるだろう。
人類全体で見るとあまりに多様性が大きすぎてフォーカスが不可能に見える問題でも、日本人として、縄文時代にスタンスをおいて考えることで解決の糸口が見えてくる場合がある。いくつかの家族が集まって集落を作り、周辺の自然を有効活用しながら、人間同士の「顔が見える」関係をしっかりと維持していた縄文時代。戻ろうとしても、もう決して戻れない縄文時代・・・。
さて今回は、茅野市にある「尖石(とがりいし)考古博物館」を訪れる。数千年にわたって豊かな縄文文化を育んだ八ヶ岳山麓には多くの遺跡が点在するが、その中心的な位置を占めるのがこの考古博物館だ。以前、このブログの「縄文の食事サンプル」でも紹介したことがあるが、実際に訪問するのは今回が初めてだ。
人気の「縄文のビーナス」が、つい最近フランスの展覧会から戻ったばかりだったので、さぞかし混雑しているかと思いきや、平日だったこともあって見学客はぼく一人だけ。博物館の館長、守矢昌文さんに 30 分以上も時間を割いていただいて、マンツーマンで説明してもらうという贅沢な時間を過ごした。
最後の氷期が終わったのは、約一万年前。これ以降、人類は、多少の地域差や上がり下がりはあるけれども、比較的暖かくて安定した環境を数千年の長きにわたって享受することになる。日本でもこの時期に、新石器時代から縄文時代への移行が始まる。実はもっと早い時期の土器も発見されているので、縄文時代がいつ始まったのかについては今後も議論が続くだろう。
約 6000 年前には気候の温暖化がピークを迎え、それから約 1000 年間、縄文文化が華々しくその最盛期を迎える。そんな縄文時代の中でも最も恵まれた時期に作られた傑作が、今回のヒロイン「縄文のビーナス」なのだ。その名の通り人を惹きつける魅力に溢れた土偶だが、制作者(おそらく女性)は、もちろん美術品として作ったのではない。祭祀に使われたのはほぼ間違いないだろう。

上半身に比較して、下半身がとてもふっくらして大きい。これを創造性に溢れたデフォルメであるとか、妊娠した女性の豊満さを表現したとか、言い方は色々あると思う。でも守矢氏によると、この形にはある種の必然性があるという。つまり、この土偶は自立型なので、これくらい「下半身デブ(失礼)」にしないと倒れてしまうのだ。実際に粘土をこねて自分で作ってみると、それがよく分かるらしい。自立させるための縄文人の工夫と技術により、必然的にこの造形となった。

頭に載っているかぶり物。渦巻き模様が描かれている。たぶん何らかの呪術的な意味があるのだろう。ただの装飾模様でないことは確かだ。ビーナスの肌を見ると、ラメのようにキラキラと輝いているのが分かるだろうか。粘土に雲母が混ぜられているのだ。器や絵画に金箔を使う日本人の感性が、縄文の土偶にすでに現れている。写真では到底表現できない肌の質感に、ぼくは思わずうなってしまった。
次に、ビーナス像でぼくが最も重要だと思う「顔」に注目してみよう。ビーナスの顔は、この土偶のオリジナルではない。縄文時代のこの時期には、「顔面把手付深鉢形土器(がんめんとってつきふかばちがたどき)」というタイプの土器が、中部地方から関東にかけてたくさん出土している。人面の把手(とって)が、深鉢土器に付属しているのだ。


左は、相模原市大日野原遺跡出土(画像:東京国立博物館)、右は岡谷市海戸遺跡出土(画像:岡谷市立博物館)の、それぞれ「顔面把手付深鉢形土器」。遠く離れた場所から出土したにもかかわらず、つり上がった目と「おちょぼ口」の造形と顔の印象がよく似ている。見ての通り、縄文のビーナスにそっくりだ。


左は、塩尻市平出遺跡「顔面把手付深鉢形土器」で、右は岡谷市立博物館所蔵の「顔面把手」。これらは同じ長野県内の出土で、場所もそれほど離れていない。眉毛と思われる造形に共通点が見られる。これらは、縄文のビーナスも含めて、当時の社会における「優しい女神様」つまり豊富な食物や子宝をもたらしてくれる「地母神」の顔を表しているのだ。
子孫繁栄を象徴する妊娠した女神、五穀の実りをもたらしてくれるありがたい女神、崇めることによって集落を守ってくれる地母神。多くの縄文人が共有したと思われるそうした女神のイメージが、この独特の顔と表情に集約されている。そうした地母神が憑依したシャーマンの表情だという主張もある。そう言われてみれば、そんな風にも見える。

画像:ベルサイユのばらより
ちょっと昭和に逆戻りかもしれないが、アニメの世界における優しくてかわいい女の子の顔は、目がパッチリと大きいこのタイプでほぼ決まりではないかと思う。ぼくらの時代にこうした顔が美人のステレオタイプであるように、縄文自体の人々にとっては、縄文のビーナスや把手の顔面に見られる顔や表情が、強くて、優しくて、美しくて、慈悲深く、おかあさんのような女性(地母神)の典型的な姿だったのだろう。
さて、縄文時代の中期(5000 年前ごろ)から中期にかけて、縄文人は何度か小規模な寒冷化に見舞われるようになる。縄文のビーナスが発掘された棚畑遺跡を含む信州の八ヶ岳山麓で発展した大集落や、青森の三内丸山遺跡に見られる大集落、そして水月湖の近くにあった鳥浜貝塚の大集落も、この縄文中期の寒冷化によって徐々に衰退してゆく。
そんな縄文中期の後半に出現したのが、次回のブログで紹介する「仮面の女王」なのだ。当然ながら土偶の製造技術は大きな進歩を遂げ、背景にある精神文化は複雑さを増し、土偶の持つ意味の「読解」は困難を極める。そんな仮面の女王が、博物館では縄文のビーナスと同じ部屋に展示してある。個人的には「これはないよ!」と思うのだが、詳しいことはまた次回に・・・。